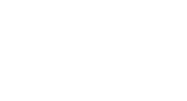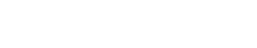講座・ワークショップ詳細
「ロマン派への誘い~盛岡公演に寄せて」小山実稚恵インタビュー

今回のリサイタルを前に、今の想いやプログラムについてなど、小山さんにお話しを伺いました。
*** コロナ禍のこの3年は、様々な経験を余儀無くされました。コンサートや公演がようやく戻りつつある今、どのように感じていらっしゃいますか。
コロナ禍の最初の頃は、集いの場がないこと、人と人との触れ合いの中で話しができない辛さを痛感しました。とにかく何をするにも、感覚的にも気持ち的にも潤いがないのです。それまでは意識すらしていなかったごく普通の触れ合いが、どんなに素晴らしいものであるかを、コロナ禍で思い知らされた気がしました。コンサートの2時間をホールで過ごす時間がどんなに幸せだったかを、ひしひしと感じました。コンサートという場があればこそ、同じ場に居合わせる者同士で音楽を共有し合うことができる。生の音楽の感動がある。人間は五感を全て使って、感じているのです。
音は、その振動が空気を通じて伝わって響いてゆきます。音楽はどこでも聞くことはできます。イヤホンでも音は聴けますが、コンサートで聴く音楽は、耳だけではなく呼吸や息遣いなども含め、身体全体で感じながら受けとめるものです。奏者と聴き手の両者が、音を感じながら音楽を聴くのです。ホールに居る人たち、そしてコンサートの製作に携わる人、コンサートへの全員の想いがあって演奏が成り立つのです。全てが一体となった時に音楽が創られ、コンサートが創られると私は思っています。コロナが落ち着き、今また、そういう一期一会の場が戻ってきたことが、なにより嬉しく思えます。
*** 今回、盛岡市民文化ホールでは5年ぶりのリサイタル。プログラムを決めていく時に、どんなことを意識していますか? 今回の選曲に込めたテーマや思いなど教えてください。
最終的にはその時に弾きたいと思う作品でプログラムを作ることになりますが、実は私はコンサートを聴くのが大好きなので、自分がコンサートで聴いてみたいと思うようなプログラムを作ることも多いです。常に両方のイメージを合わせている感じでしょうか。
シリーズの場合は回ごとの展開を考える楽しみもあります。また、数年に1回のリサイタルなどであれば、その1回の演奏会がより結実したものとなるように、興味が高まるプログラムになればと思っています。
今回のプログラムは、ロマン派の極み。ブラームスの間奏曲は今回のプログラムの青写真というか、一つの演奏会の導入としてイメージを導くための小品です。そしてロマン派の傑作シューマンの「ファンタジー(幻想曲)」。3楽章の静寂の終わり方がとても気に入っています。プログラム第1部は静かにハ長調の響きで夢想の中に消えて、新たに第2部をショパンのソナタで決意を持って始めるのが素敵かなと思って決めたプログラムです。
*** 小山さんにとって、ブラームス、シューマン、ショパンは、それぞれどんな作曲家ですか?
ブラームスは、深く温かく、静かに一歩下がったところから思いやる“思いやり”ですね。温かさと優しさを感じます。優しさといってもエレガントな表面的な優しさではなく、もっとじんわりとしている。ショパンよりも湿り気を感じます。ブラームスは森の土とか雨に濡れた緑の葉のような・・・。
シューマンは、一言で奇才ですね。研ぎ澄まされていて魅力的で繊細で、人間本来の感情の起伏が伝わってくるのです。静と動、安らぎと不安・・・という感じで絶えず対極の感情が支配して、生き方も刹那的です。だから、クララのようなどっしりとしたおおらかな女性に憧れたのかもしれません。シューマンの曲はキューっと胸を締め付けられる瞬間がたくさんありますね。それがとても魅力的なのです。色で言えば、草木のような自然の色合いの曲もあれば、初期の傑作「カーナバル(謝肉祭)」のようにとても鮮やかな原色を感じる曲もあります。だけどこの「幻想曲」は原色ではなく、霧や靄が漂うような幻想の世界。クララとの結婚に悩み、精神的にも辛く混迷の時期につくられた背景も影響しているかもしれません。
ショパンは、やはり真の天才です。美意識が高く毅然としていて、誰が見ても聞いても感じても美しい。優しさもあるけれど、無駄なものや説明的なものはなく、迷いがあったとしても曖昧にはならない。ショパンの迷いは、それが美しさになってしまうのです。すべてがダイヤモンドのように特別な質感で希少。美しさの極みです。初心者や初級者ももちろん美しいと感じますが、極めた人が感じる美しさの深みがあります。ショパンは触れるほどに魅力が尽きないのです。
*** 小山さんに選んでいただいた盛岡市民文化ホールのピアノも25歳となりました。各地の演奏会では毎回違うピアノでの演奏となりますが、ピアノとの向き合い方として意識していることはありますか?
そこで育ったピアノと、いかにコンサートまでの間に仲良くなれるか、ということに尽きるかと思います。演奏経験のあるホールの同じピアノであっても、演奏の度に違いを感じます。ピアノはもう人間と同じですよね。生きているのです。
ピアノのボディーは木でできていますから、気候の変化や年数の経過など様々な影響を受けます。楽器として作られた性能は確固としてありますが、たとえば使い込まれた手工芸品の手触りが変化して、時と共にまろやかさを増すように、ピアノの状態も変わってゆく。その時その状態を感じ取りながら接しています。毎回が違うので、いつも再会の喜びがあります。
*** 最新リリースのCD「モノローグ」は、ご自宅にある130年ほど前のピアノでの演奏と録音となったのはとても興味深いのですが。
今回のCD録音で使用したピアノは、ちょうどコロナ禍の間に出会ったのですが、古い昔のなんとも言えない味わい深さがとても気に入りました。音色や響き、音を出してからの余韻など、心が伝わる感覚が感じられたのです。素材や保存状況も良かったのだと思います。このピアノに合わせて曲も選びました。
*** リサイタルのほかに、現在取り組まれているプロジェクトには、コンチェルト・シリーズや室内楽などがありますが、それぞれにどんな魅力を感じていらっしゃいますか?
ソロやコンチェルト、そして室内楽のコンサートが、別の区分けであるとは思ってはいません。音楽は音楽。ひとりで演奏するか、皆と一緒に演奏するかの違いだけだと思っています。
音楽は出会いなので、最終的に音を出してみてどうなるか。その出会いの中に身を委ねて音楽を共有して演奏する、自分の感じることを出す、ということなのかなと思うのです。当然のことですが、一人で演奏する場合でも毎回同じ弾き方にはなりません。コンチェルトや室内楽ならなおさらです。いろいろな方々と一緒に音楽をつくりあげていくわけですから、どんな演奏になるかは音を出してみないとわからない、というか音を出してみて初めてわかるのです。
音楽の楽しみはそこにあると感じています。どんなコンサートでもリハーサルはもちろん行いますが「本番は本番」というところが音楽の醍醐味ではないでしょうか。
*** ピアニストを目指す盛岡の子どもたちにアドバイスするとしたら、どのような言葉を?
私は、盛岡でピアノを始めていなかったら、今ピアノを弾いていなかったのではないかな、と思うことがあります。それぐらい、一つのものに集中して取り組む環境というか、ピアノなどをやるにはとてもいい場所だと思っています。自然が多く、時の流れ方がおだやかなのです。
本来、芸術が最終的に行き着く先は、そのもの(こと)をどれぐらい好きか、どれだけ愛しているか、それしかないと思うのです。だから芸術に集中できる環境は最高です。
子供の頃の差は、一年がとても大きく感じられますから、若いほどに天才のように見えることがあります。でも、芸術は一生かけて追い求めるもの。最終的にどこまで進めるかなのです。盛岡だからこその、そういう気持ちを大事にしてもらいたいと思います。
*** 最後に盛岡のお客様にメッセージを。
ロマン派の3人のそれぞれの音楽を、お客様それぞれの思いで自由に聴いていただけたら・・・。マリオスのホールで、一期一会の音楽を皆様と共に作っていきたいと思っております。
*** とても興味深いお話を伺うことができました。今回のリサイタルも一期一会の豊かなひと時になることを願っています。貴重なお時間をありがとうございました。
公演情報はこちらからどうぞ!
小山実稚恵ピアノ・リサイタル
講座・ワークショップ一覧に戻る